【9月の勉強法】
9月の初めに受けた東進の阪大本番レベル模試で初めてC判定を取れて、この頃は自信に満ち溢れて勉強がとても楽しかったです。
最初の週には学校の定期テストがあったので、その勉強をしっかりしていました。
それが終わってからは、秋模試に向けた勉強を始めました。
特に力を入れたのは日本史で、圧倒的に論述の練習量が足りていなかったので、『スタートアップ 日本史 論述問題集』(駿台文庫)だけでなく、『日本史の論点』(駿台文庫)という教材を用いて勉強していました。
日本史はもともと得意で勉強自体は苦ではありませんでしたが、流石にもう少し早くしておくべきでした(というのも結構時間がかかるから)。
英語と国語は通常授業の予習・復習のみをしていてまだ過去問には取り組んでいませんでした。
また9月から南先生の「高3共通テスト地理」の授業を受け始めました。
僕は、メモを取ることよりも独学では理解できないような因果関係を聞いて自分で理解することに集中していました。
惰性で授業を受けるよりも受け方を工夫することも成績向上の一つの鍵になります。
【10月の勉強法】
流石に入試が近づいてきて少し焦ってきました。
なぜなら数学を完全放置していたのをこの時気付いたからです。
「高3共通テスト数学」を9月から受講していなかったら僕の数学はとんでもないことになっていたかもしれません。
阪大文学部は二次試験で数学の代わりに社会受験をすることができるので数学の優先順位は低かったですが、他の文系学部を受ける人は数学から逃げないようにしましょう。
僕はもう手遅れだと思って、『緑チャート』(数研出版)を必死にしていましたが、研伸館の「高3共通テスト数学」の11月以降の授業内演習の点数が変わらず絶望していました。
英語については、10月に初めて阪大の過去問を解きました。
「高3京大阪大・医学部英語」で難易度の高い読解に取り組んでいたおかげか手も足も出ないだろうなと思っていた阪大英語がいつの間にかスラスラ解けるようになっていました。
この頃に理科基礎の勉強もちゃんと始めました。
もともと少しずつ勉強していたおかげで基礎の穴抜けは少なく、スムーズに問題演習に移行できました。
秋模試に向けた勉強はもちろん大事ですが、共通テストでしか使わない科目もこの頃から少しずつ取り組んでおくといいと思います。
【11月の勉強法】
11月になって変わったのは、阪大の総合型選抜の対策を始めたことくらいです。
12月15日に阪大で小論文試験と面接があり、事前に志望理由書や文学部に関する探究の成果等を提出する必要があります。
最初はすぐ終わるだろうと思っていましたが、なかなか終わらなかったため早めに始めて良かったと今でも思います。
一番手強かったのは間違いなく小論文です。
120分の制限時間で1200字程度の記述が求められるため、対策を始めた当初は制限時間内に終えることができなかったり、自分の記述が論点に添えてなかったりと調子が悪く、本番までに改善できるのか不安でした。
阪大(総合型選抜・学校推薦型選抜試験問題)の過去問4~5年分、東大文学部の学校推薦型選抜についての課題1~2年分にじっくりと取り組むことで、ある程度の自信をつけて試験に臨むことができました。
また中旬には駿台の阪大実戦と河合塾の阪大オープンがあったので、それに向けて阪大の過去問を英語・国語とも1年分ずつ解きました。
実戦はE判定でオープンはB判定でした。
その後は模試の復習を兼ねて弱点だと思った英国社の二次試験対策と理科基礎や数学の共通テスト対策を両立させていました。
冠模試の後の復習は模試を受ける以上に大事です。
模試を受けることを目的とせず、結果から合格までの道のりと達成すべき課題を明確にすることが模試を受ける本当の目的だと今僕は思います。
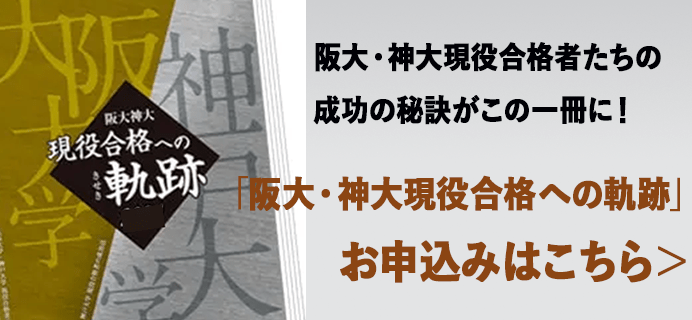
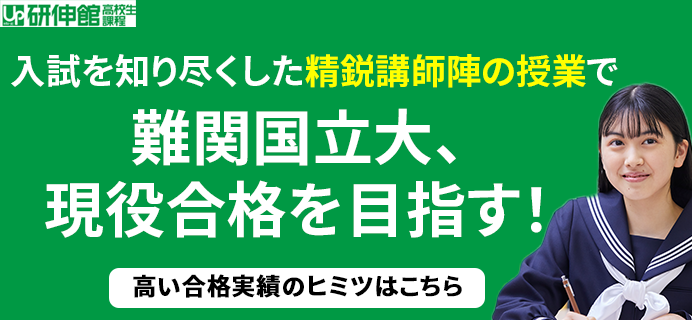
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。
