「高1の11月~2月ごろまでの過ごし方」
【総合的な勉強法】
高1はまだ受験まで日が残っていて、実際に、そこまで受験を意識する必要はないように思います。ただ、受験勉強が本格化(高2夏すぎくらいでしょうか)してきた時に、スムーズに切り替えができるように勉強の習慣化を心掛けるようにするのをお勧めします。学校の定期考査でしっかり点数を取り、どの科目についても、基本的な事項を押さえておけば、高2になっても困らずに勉強に取り組めると思います。
余裕があるならより発展的な内容に着手すればいいと思いますが、まずは焦らずに基本を固めましょう。
「高2の11月~2月ごろまでの過ごし方」
【英語・数学の勉強法】
英語:英単語・文法を固めつつ、与えられたものをこなしていればそれなりに力はつくと思います。苦手意識があるならば何度も文章を読み返すなどして、英語に慣れましょう。その時、丁寧に意味をとって、分からないままにしておくことがないようにしましょう。僕の場合、分からない単語や表現、文法事項は別でノートにまとめて、後から見返せるようにしていました。復習しやすいのでお勧めです。
また、共通テストになってリスニングの重要性が増したかと思います。リスニングも英文を読むのと同様で、一朝一夕で習得できるものではないので通学中や隙間時間を利用するなどして聞く習慣を身につけましょう。「TED」とか、「BBC」とか、材料はたくさんあると思います。僕はさぼってしまったせいで、直前かなり困ったので、そうならないように頑張ってほしいです。
数学:標準レベルの参考書を利用するなどして、高3になるまでにしっかり演習を積み、基本的な公式や定石をマスターしておきましょう。文系だと数学が得意でない人も少なからずいると思いますが、数学で大きく差をつけられてしまうと、よほど他の科目が秀でていない限り、埋め合わせるのが大変です。高3になってから基本を見返す時間はないと思って、真剣に取り組んでほしいです。できると思っている範囲でも実は基本ができていなくて、難しい問題に直面した時に困ってしまう、ということは意外とあります。
【副教科の勉強法】
できるだけ英語・数学に力を入れた方がいいという意味で、そこまで必死に取り組む必要はないように思います。しかし、後にも書いているように完全に手を抜いていると、高3になってから大変なので、授業をしっかり聞くくらいの努力はしましょう。社会であれば、簡単に流れを押さえるくらいの意識(歴史なら、時代感覚をつけられるとなお良いと思います)でいいです。
受験に対する意識もまだそこまで高くないうちから、いきなり一つ一つの単語を覚えておこうとしても難しいですが、雰囲気だけでも覚えておけば高3からいいスタートを切れると思います。
【今にして思う後悔、そして、高2生へのメッセージ】
社会を高2の間に少しでもやっておけば良かったなと思います。学校の授業をちゃんと聞かずに、ほとんど0の状態で高3に突入してしまったせいで、高3は社会ばっかりやる羽目になり、他の科目に時間を割けず、もどかしく思うことも多々ありました。
ただ、このような状況でありながら何とかやってこれたのは、主要科目の基本がしっかりしており、復習に時間をかける必要がなかったからだと思っています。しつこいですが、それくらい基本が大事です。
あとは、勉強科目が偏りすぎないことが重要です。苦手科目ができてしまうとどうしてもそれに時間をかけて、得意科目は放置ということになりかねないですが、こうなると成績が安定しません。そういう状況にあっても、必ず、短くてもいいので、すべての科目に時間を割くようにすることお勧めします。
最後に、高3になるとアドバイスを受ける機会が多くなったり、より周りが気になったりすると思います。が、それらを鵜呑みにしてしまうのではなく、自分の頭で考えて取捨選択する癖をつけてほしいと思います。頑張ってください。
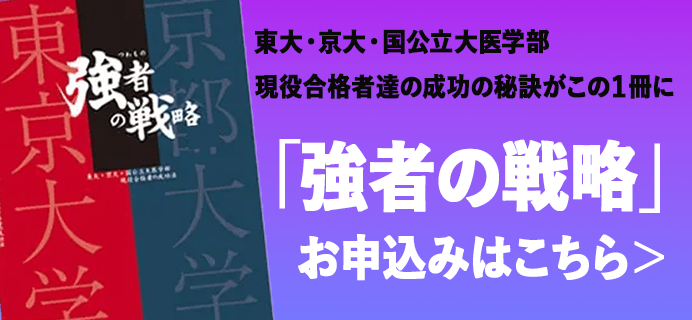
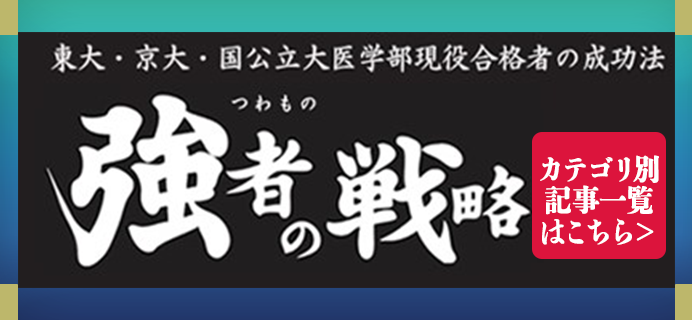
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。
