【秋模試(オープン・実戦など)~共通テストまでの学習法】
直前期に共テ対策一色になると二次対策への切り替えが難しくなると考え、秋および直前期の1月は共テ対策を中心に据える一方、12月以降には二次対策との並行ができるようにスケジュールを組みました。共テの得意科目(英語・国語)での失敗により意気消沈・動揺するのを防ぐべく、得意科目の共テ対策を重視し、立ち読みして厳選した後に購入した各社のパック問題集を用いて、国語は秋、英語は12月頃から年末にかけて長期スパンで対策しました。
この時期設定の理由は、1月に、二次試験では使わない理科基礎の暗記や苦手意識のある共テ数学の詰めに時間を割くためです。(なお、パック問題集は科目ごとに版元を使い分けました。)国語は1問ごとの配点が大きいため、知識の抜け漏れや読解の内容に関する選択問題の誤答の傾向を確認・分析しつつ、優先的に対策するとよいと思います。速読力が鍵となる共テの英語(リーディング)に関しては、英字新聞を読んで速読の練習をしていました。
模試やパックの問題の音声を朝食時に流すなどしてリスニング対策も行いました。数学に関しては、研伸館の授業の予習・復習で二次対策をしつつ、1社のみ共テパックを購入し、時間を計って解きました。
また、「メジアン数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B・C」(数研出版)も日常的に解き、基礎の確認をしていました。理科基礎に関しては、学校の授業の教材の良問をスクラップし、定着に自信がない知識と共にノートにまとめていました。学校の教材を解説まで読み込み、最大限に活用することを意識していました。
理科基礎の解説の時間を利用しこうした作業を行うことで、時間も有効活用できると思います。ただし間違えた問題や偶然正解した問題の解説はよく聞いていました。情報に関しては、愛用していた学校教材の「ベストフィット情報Ⅰ」(実教出版)や学校配布のプリントを、2~3週間に1回ほど一括で見直していました。
最後に社会に関して。共テ&センター地理の過去問は夏休みに散々解いたので、秋以降は約2社のパック問題集を解きつつ、2次対策に重点を置きました。メルカリで購入した他塾の東大地理の教材や、京大・東大の模試および本番の過去問を使用し、学校の先生の添削を受けることもありました。
日本史に関しては、ネット上で閲覧できる共テ&センター過去問はすべて解きました。12月以降には赤本にも取り組みました。
【共通テスト前日、眠れたかどうか】
ちゃんと眠れました。
【共通テスト当日に持っていったもの】
1日目:正誤をチェックし復習が必要な箇所をハイライトしたものの復習しきれなかった分の、国語・社会のパック問題集の問題・解答冊子。国語については、解く際の注意点をまとめた紙、および自習や学校の授業の際に書き溜めた古典の知識のまとめノートも持参。
2日目:理科基礎のまとめノート、『FocusGold』(啓林館)の統計の章(裁断しました)、『ベストフィット情報Ⅰ』(実教出版)の解答編。
【共通テスト当日の過ごし方】
休み時間は、目が疲れない程度に勉強しました。学校単位での申し込みのため、同じ学校の人が周囲に多かったものの、ほとんど話しませんでした。個人的には、試験の出来などについては特に、話さない方が良いかもしれないと思います。
【昼食をコンビニで調達した人に質問です。何を購入しましたか?眠くならないようになど気をつけたのか?】
両日とも、好物入りの親の手作り弁当を持参しました。
【共通テストの1日目の帰宅後の過ごし方】
理科基礎や情報を中心に、最後の確認を行いました。夕食には、好物の鴨鍋を食べました。疲れて頭痛がしたため、早めに就寝しました。
※2日目:共テボケを防ぎ、翌日以降の勉強のリズムをつくるため、学校教材の「メジアン数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・B・C」を使用し、二次試験の数学の中堅問題(頭は使うが負荷少なめ)を解きました。当日に疲労困憊でない限りは、共テ対策と二次対策の学習のゆるやかな接続としてこの類の勉強を少しするのはおすすめです。
【共通テスト当日の思い出や珍事件】
2日目に2時間程早く到着してしまいました。会場が開いていない事に気づき現場のスタッフと話したことで、自分が集合時間を間違えたことに気が付きました。しばらく屋外で待機していましたが、その後親に車で迎えに来てもらい、数学の統計分野の復習をしつつドライブをしてもらい時間を潰しました。早く到着したのでまだ良かったものの、逆に遅かったら詰んでいました。文系・理系で集合時間が違うと思うので、受験生の皆さんはくれぐれも気をつけてください!
【共通テストの受験会場はどこでしたか?】
京都大学
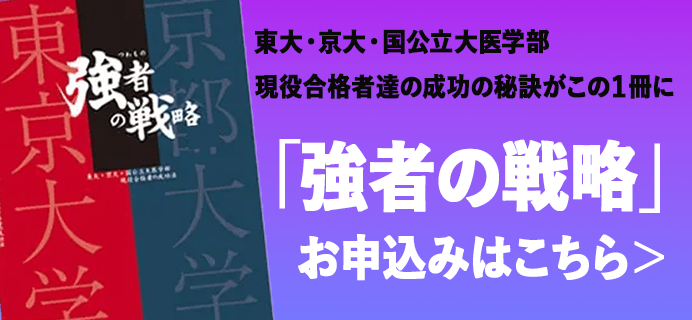
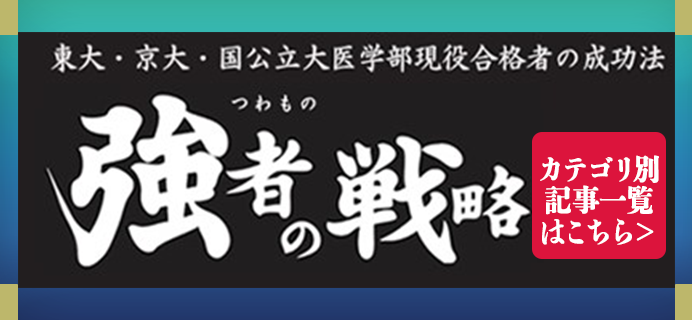
この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。
